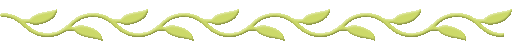
| 音楽と農業の関係―自然のハーモニーと人間と― 音楽に想いを乗せて さて、ここでは前ページから登場している「ブロードキャスター」という装置の背景について、もう少し説明したいと思います。 装置の正式名称は「クォンタム・フィールド・ブロードキャスター」といい、これは、米国の科学者トマス・ガレン・ヒエロニムス氏の「コズミック・パイプ」という発明品をもとに旧オーストリアの哲学者ルドルフ・シュタイナー氏の農業理論を取り入れて、米国のヒュー・ラベル氏によって作られました。 トマス氏は「有機的エネルギーという物が存在し、それは(そのエネルギーの持つ波動の)周波数を合わせることによって自在に集めたり放射することができる」ということを発見した人です。 また、ルドルフ氏は俗にいう「シュタイナー思想」を提唱し、教育や芸術・農業について様々な考察を残した人です。その理論を取り入れた学校や農場は世界各地にあり、かのミヒャエル・エンデはこの学校の出身であることはつとに有名です。彼は月の引力をはじめとする天体の波動の影響とそれを活用することで、植物や動物が本来持っているべき波動のリズム(原型パターンと言います)へと導くことを主眼とした農業を提唱しました。それは「バイオダイナミック(生命力学)農法」と呼ばれ、その特徴をごくごく簡単に言うと、農作業のあらゆる作業、たとえば種まきをするのに適した日時を天体の動きに呼応したカレンダーによって決めたり、また農場の環境を改善しより生命力の高い農作物を作り出すために「調合剤」と呼ばれるいわば「土壌・空間波動修整液」ともいうべきものを用いたりします。そうして得られた食物を食することで、ひいては、人間の精神性をも向上させよう・・・という壮大な氏の思想を背景にによって現在も研究され続けているこの農法ですが、残念ながら、その実際は学ぶべきことがあまりにも多く、なかなか取り組みにくいのが現状のようです。 その農法をよりたくさんの人に取り組みやすく、また、「調合剤」の波動のみ増幅しを放射することによって広大な農地にそれを播く労力を減らす方法を編み出したのがヒュー氏です(この方の考察を突き詰めていくと、ある意味私の相棒が取り入れている「無肥料栽培」の理論が証明できそうなことに気づきました…完全な余談ですが)。 これ以上の詳しい説明は割愛しますが、私がブロードキャスターの働きの中でもう一つ注目しているのが、この装置が調合剤の波動だけでなく、農地所有者の意図・想いをも増幅し農地に伝えることができるという点です。それにはどうするかというと、設置する際、筒の中に所有者の環境に対する願いなどを記入した意図書を入れておくのだそうです。逆に、筒の中に殺虫剤などを入れておいてとんでもない(!)結果になった例もあるとか・・・。 パンフルートも、息を吹き込む時の吹き手の気持ちや体調をダイレクトに表現してしまう点はまさにこの装置とそっくりで、このことは私自身痛いくらい身にしみて知っています。それゆえに同じ楽器でも吹き手によって全然音色が変わってしまう個性の出やすい楽器であり、そこが逆に怖い点でもあります。ある程度の精神修行というか、本当に生半可な気持ちで安易に吹いてはいけない「聖なる楽器」だとつくづく感じます。その点、ブロードキャスターはシンセザイザーの自動演奏と同じで体調の変化はなく扱いやすいありがたい「楽器」(注)ですが、私自身はそれでも、人間的なこのパンフルートの方がなんとなく好みではあります。ただ単に自分で吹きたいだけ?からかもしれませんが・・・はたして、この笛を自動演奏したらどんな音色になるのでしょうか。 パンフルートに心こめて息を吹き込む時、その音色とともに吹き手の想いも風に乗って伝わっていく・・・作物たちの声に耳を傾け、その声に応えるように農地に向かって吹くとき、きっと素晴らしいことが起こるような気がしてなりません。古代中国ではその形は鳳凰からとったとされ「簫韶九成せば、鳳凰来儀す」と言われる「神を祀る楽器」だったのですから。いずれ、実験的な試みではありますが、本格的にやってみたいと思っています。その姿は遥かアルカディアの森で、牧神パンがパンフルートを吹き始めると小鳥や動物たち・妖精たちが集まってじっと耳を澄ましていたという風景に重なり、自然のハーモニーと人間との懸け橋としてのこの楽器の隠された役割を体現することになると思います。 ちなみに、ルドルフ氏は彼のもう一つの分野である芸術思想で用いられたライアー(千と千尋の・・・で一躍有名になった竪琴です)をはじめとする楽器や音楽と、農業との関係は直接語ってはいないようです。しかし、農業に関する考察も未完のまま亡くなってしまったところからみると、もっと長生きされていたら、本当は語られるべきものだったかもしれません。残念です。天体の動きと農業の関係も現在、「月」のみと対象は限定されてしまいますが、研究がかなり進んできているようです。それを思うと、牧神パンが月神セレネー(ローマ名ルナ)を羊皮を被って毛むくじゃらの体をカモフラージュしてまで逢引きしたという神話の理由もわかります。ただ単に性欲が強く関係を迫ったわけではないのです。月の力が農業とかかわりが深いことを、古の人は知っていたのです。 (注) ブロードキャスターを日本で広める運動を展開しているHPで、「ブロードキャスターを詩的に表現すると《宇宙の愛の調べを奏でる大地のフルート》とでもなるかもしれません。実際、ブロードキャスターにはいろいろな楽器がいっぺんに使われているようなものなので、《大自然調和交響楽団》と言ってもいいでしょう。」との表記がされていました。表記者も「楽器」というとらえ方をしている点、とてもうれしくなりました。形に違いはあれど、自然を想い、癒したい気持ちは共通ですね(ブロードキャスターについて、勝手にいろいろコメントしてすみませんでした)。 メロディーの力 さて、音楽や波動の持つ力と農業との関係というと、「植物にクラッシック音楽を聞かせるとよく育つ」という話を思い浮かべた方も多いと思います(と、いうより、こっちのほうがむしろ一般的ですよね・・・普通)。例に挙げるならばモーツアルトの曲が有名ですね。そのメカニズムは良くわかっていないのですが、一説によると、タンパク質の分子構造をメロディーに置き換えたとき、クラッシック音楽の旋律に近いものが出来るということで、そのためではないかという研究がされているそうです。その考えを応用すると、「聴くだけ病気が治る効く音楽」が出来るとか…。逆に、知らず知らずのうちに耳に入ってくるノイズの中に病気になるメロディーが含まれていることがあるそうで、ちょっと怖い話でもあります(「タンパク質の音楽」筑摩書房刊より。HPもあります)。 詳しい理屈は抜きにして、一般的にいいとされる音楽のメロディーを聴くと気持ち良くなるのは、やはり生き物共通の原理というべきなのかもしれません。植物にいわゆる「耳」はありませんが、「音」とは、言い変えると「空気を震わせる振動」のこと、でしたね。むしろ植物の方が体全体にこの空気振動を感じ取るため、敏感に反応するといいます。アメリカの先住民族であるホピ族の古老は、トウモロコシに歌いかけ育てているとか…。私もよく畑で野菜に「あっ、踏んづけてゴメン」なんてひとりごとみたいに話しかけたりしていますが(笑)。 そこで、畑の植物にパンフルートを聞かせてみようと思い立ち、実際に畑に立ってみました。と、困ったのが、聞かせてみたい曲がない!!あえて浮かんできたのがジョン・デンバーの「緑の風のアニー」ぐらい・・・。そうです。音楽の曲というと、「人間が人間のため」に作ったものがほとんど。「植物が聴く」という観点に立って作られたものなど存在していないに等しいことに気がついたのでした。これでは作曲から始めなければならない、ということで、これでは本格的な演奏までかなりの時間がかかりそうです・・・。とほほ。 ところが、実際にしかも牧神パンが吹く曲を聴いたという人物がいるのです。それによると、「ひどくつかまえどころのないメロディーなの」だそうですが・・・その方の話は続いての章にてじっくりすることにしましょう。 NEXT パンフルートが響く世界に―牧神パンの想い―のページへ 聖なる笛パンフルート―牧神パンと私―目次 パンフルートってどんな楽器?―その姿と名の由来― 悪魔にされた牧神パンの話―ギリシャ神話から現代まで― 音楽と農業の関係―自然のハーモニーと人間と― パンフルートが響く世界に―牧神パンの想い― おまけ―牧神パンがくれた恋?― ☆ |
 トップページへもどる
トップページへもどる